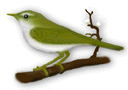 |
専徳寺の庭でもウグイスのさえずりが聞こえ始めました。 まだ「ケキョケキョケキョ・・・」というウグイスの谷渡りと呼ばれる鳴き方は聞かれませんが、このウグイスの鳴き声、この声を誰もが「ホー、ホケキョ」と鳴いていると思っているんではないでしょうか? これは、「ホー、ホケキョウ(法、法華経)」と鳴いていると、昔の人が聞いて、それがそのまま伝わってきているんです。 これを「聞きなし」といいます。 昔の人は鳥の声を言葉に置き換えることをしていました。 ホオジロは、「一筆啓上仕候(いっぴつけいじょうつかまつりそうろう)」とか、「源平ツツジ、白ツツジ」と鳴いている。 コジュケイは、「ちょっと来ーい、ちょっと来ーい」。 ツバメは、「土食って虫食ってしぶ〜い」。 ホトトギスは「てっぺんかけたか」。 このように鳴いていると、昔から言われています。 よーく聞いてみると、そんなふうに聞こえるような・・・。 |
 |
また、そんな鳴き声から名前が付けられた鳥もいます。 サンコウチョウというしっぽの長い瑠璃色の鳥。 この鳥は、「ツキ、ヒ、ホシ、ホイホイ」と鳴いているように聞こえるので、「月・日・星」の三光。それでサンコウチョウ(三光鳥)と名づけられました。 |
また、仏教にまつわる鳥達もいます。
ブッポウソウ(仏法僧)というありがたい名前のついた鳥。
この鳥は、昔、山から「ブッポウソウ、ブッポウソウ」と鳥の声が聞こえてくるけど、どんな鳥が鳴いているのか分からない。よっぽどありがたい姿をしているんだろうと思っていると、その鳴き声のする近くで、瑠璃色のとてもきれいな鳥が姿を見せます。
それで、この鳥が「ブッポウソウ」と鳴いているに違いない。ということで、この鳥が「ブッポウソウ(仏法僧)」と名付けられました。
昭和10年になって、何と「ブッポウソウ」と鳴いていたのは、このきれいな鳥ではなく、コノハズクというフクロウの仲間だったということが分かったんです。千年以上も勘違いで名前が呼ばれていたんです。
それでも名前を改めず、ブッポウソウのことを「姿のブッポウソウ」、コノハズクのことを「声のブッポウソウ」と呼んでいます。
ブッポウソウ
コノハズク
| それから「ジュウイチ(十一)」というホトトギス科の鳥がいます。 この鳥は、別名を「慈悲心鳥(じひしんちょう)」といいます。 それは「ジュイチー、ジュイチー」という声が、「ジヒシン、ジヒシン(慈悲心、慈悲心」)と聞こえたからだといいます。 |
| こんなふうに、昔の人は鳥の声を聞いて、言葉に聞きなしてたんです。 だから、ウグイスの声は「法、法華経」。 でも、この「ホー、ホケキョ」と鳴く声を、ほかの言葉で聞いた方がおられます。 |
|
| 本願寺第八代宗主、蓮如上人です。 時は、蓮如上人がお亡くなりになる明応8年のこと。 蓮如上人が病の床につかれているところへ、弟子の空善という方が、蓮如上人の心を少しでも和ませようと、ウグイスの入った鳥かごを枕もとへ持っていきました。 蓮如上人は、そのウグイスの鳴く声を聞いて、 |
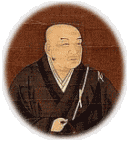 |
ウグイスが「法を聞けよ、法を聞けよ」と鳴いている。このウグイスまでも「法を聞けよ」と鳴いているのに、人間に生まれ、親鸞聖人の流れを汲む私たちが、法を聞かなかったら何ともなげかわしい。とおっしゃられ、弟子の慶聞坊に自分で書かれた「御文章」を読ませ、念仏のありがたさをしみじみと味わわれたそうです。 今でもその鳥かごは、奈良県吉野の本善寺さんに残されているとか。 |
|
| そして、江戸時代、大和(現在の奈良県)の清九郎さんのはなし。 清九郎さんは、若いころ、ばくちに負けてはやけ酒を飲むという日々を過ごしていたそうです。そんなときに、まわりで鳴くウグイスの声に、 「うるさい、朗らかな声で鳴きおって。何がそんなにうれしいんだ!」と大声でわめいては、小石を投げつけていました。 やがて清九郎さんは結婚しますが、その奥さんは産後の肥立ちが悪く、子どもを残して亡くなってしまいます。そのころから清九郎さんは聴聞をはじめました。 あるとき、奥さんの里にお墓参りにいったとき、さきほどの鳥かごがある本善寺さんにお参りしました。そこでそのウグイスの話を聞いて、清九郎さんはひれ伏したそうです。 蓮如さまは「法を聞けよ」と鳴くウグイスを大切になさったというのに、若いころの私は、「法を聞けよ」と教えてくれるウグイスに石を投げつけていた。何と恩知らずなことをしたことか・・・。 それからというもの、清九郎さんはウグイスの声が聞こえると、 「ご親切にありがとう。」と、ウグイスに返事をして、お念仏を称えたんだそうです。 |
| あなたは、この話を聞いて、ウグイスの声をどう聞きます? 「法を聞けよ」?、それとも「法、法華経」? |
2000/2/26