

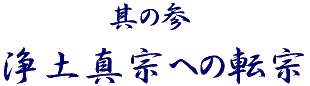
| 広島県での真宗の発祥は非常に早く、備後地方にはじまっています。元応2年(1320)、相模の最宝寺明光という高僧が、沼隈の山南に光照寺を建て、第三代宗主覚如上人の長男、存覚上人がこの地へしばらく逗留されたりと、真宗御法義の浸透が強力に推し進められておりました。 次々と真宗寺院も建立されていきましたが、当地方は小早川・仏通寺の勢力が強く、真宗の伝播は備後から三次を経て、安佐郡・山県郡等の県北へと伸びてゆきました。 この近くでは川尻の光明寺だけが、明応2年(1496)本山直属の真宗寺院として建立されていますが、その他の寺院のほとんどは他の宗派から転宗しており、しかもずっと後のことであります。 |
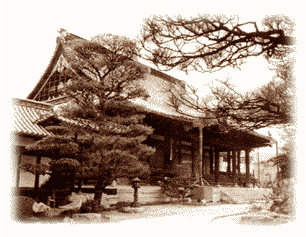
川尻光明寺
| 本願寺第8代宗主、蓮如上人の時代から、真宗教団の勢いは全国的にひろがり、真宗寺院も急速に増加してゆきました。 11代顕如上人に至って、大坂の石山本願寺と織田信長との間に石山合戦が始まる(1570)と、県北の真宗門徒は毛利元就の援護のもとに、続々と合戦に参加してゆき、教団の力は周辺へも広がってゆきました。 おそらくこの地方への勧誘や啓蒙も激しく行われたようで、念仏の声は広く大きくひろがって、寺院も次々と真宗へと転宗してゆきました。 |
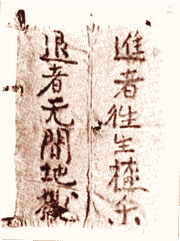
石山合戦に向かう舟にはためいた黄旗
(竹原市東野町長善寺蔵)
| 永録11年(1568)、宇都宮一族の中で、一鑑坊の兄満綱の次男善寿(俗名不詳)が出家して、一鑑坊の後を継ぎました。 念仏の輪は次第に次第に大きくひろがり、善寿も天正2年(1574)、顕如上人に帰依して改宗し、現在地へ真宗寺院の堂宇を建立しました。 山号はそのまま用い、寺号も専徳寺と改め、ここに浄土真宗嶺宿山専徳寺が誕生しました。 そのため、善寿を真宗改宗しての第1世と称しています。石山合戦が始まってから4年後のことです。 観音堂「普賢閣」は、善寿の改宗にともない、善寿の兄に当たる宇都宮三郎右衛門義綱の守護に属すことになり、累代にわたって維持され、明治維新まで毎年浅野家より米1俵が贈られていたと伝えられています。 |
| 天正8年(1580)、石山合戦終結にともない、真宗の教えはたいへんな速さで伝わり、広村の寺院も次々と真宗へ転派してゆきました。 天正8年に住蓮寺、慶長4年(1599)に善通寺と真光寺と、わずか25年の間に広村の全寺院が真宗に転宗されたことは、当時の教団の勢いがいかに強く、民衆の大きな期待に添ったものかということがうかがえます。 |